目次
戸建てにお住まいの方の心配事といえば、やはり耐震性です。こちらの記事では戸建ての耐震補強方法や費用相場、耐震工事のチェックポイント、補助金制度の活用法まで詳しく解説します。リフォームを検討中の方はぜひご覧ください。
戸建ての耐震補強とは?基本を解説
戸建ての耐震補強とは、地震による倒壊や損傷を防ぐために建物の構造を強化する工事のことです。とくに、古い木造戸建て住宅では、柱や壁、基礎などの補強が重要です。
耐力壁の追加、基礎の補修、金具による接合部の強化など、さまざまな方法があります。耐震診断をもとに、建物の弱点を見極めて補強することで、安心して住み続けられるようになるため、注目されています。

我が家は大丈夫? 耐震性のチェックポイント
住まいの耐震性は、見た目だけでは判断が難しいところです。6つのチェックポイントについて、確認していきましょう
・築年数が古い(1981年以前に竣工)
・1階の壁の数が少ない
・構造部の劣化が進んでいる
・建物の形状が複雑である
・地盤が弱い
・ちょっとした地震でも振動を感じる
築年数が古い(1981年以前に竣工)
1981年以前に建てられた戸建ては、「震度5程度の地震で倒壊しない」という古い耐震基準を基に設計されているため、大地震で倒壊する可能性があります。
建築基準法は1981年と2000年に法改正が行われ、現在は「震度6強~7程度の地震でも建物が倒壊しないこと」が基準となっています。そのため、1981年以前に建てられた戸建ては、耐震診断を受けるのがおすすめです。
1階の壁量が少ない
木造住宅では、壁の量が少ないと建物全体の剛性(※)が低下し、地震の揺れに弱くなります。とくに、1階部分に大きな開口(車庫・店舗・広い窓など)がある住宅は、壁の量が不足し、地震時に倒壊する恐れがあるでしょう。また、1階が開放的な「ピロティ構造」の場合、上階の荷重を支えきれずに倒壊する危険が高いです。
(※)剛性とは
剛性とは、物が外から力を受けても変形しにくい性質のことです。剛性が高い建物は、地震などの外からの力が加わっても崩れにくいと言われています。
構造部の劣化が進んでいる
柱や梁、基礎など、建物の構造を支える部分が劣化していると、耐震性は大きく低下します。腐食、クラック(ひび割れ)などが見られる場合は、早急な点検と補修が必要です。
とくに木造住宅では、シロアリが木材を食い荒らすことで構造の強度が著しく低下し、地震に弱くなります。リフォーム時には、補強工事や修繕を行うことが不可欠です
建物の形状が複雑である
L字型やコの字型など、複雑な形状の住宅は、ねじれや歪みが発生しやすい構造です。地震の際に揺れが不規則に伝わり、部分的な倒壊リスクが高まります。
とくに、建物の角部分や壁が少ない部分に力が集中すると、強い揺れに耐えられない可能性が高いです。
地盤が弱い
建物がしっかりしていても、軟弱な地盤では地震時に大きな揺れが発生し、傾きや沈下を引き起こす恐れがあります。とくに、造成地や埋立地などは地盤が不安定なため、十分な対策が必要です。
また、地下水位や湿度が高い場所も地盤が弱く、リフォームでは慎重な調査が欠かせません。
ちょっとした地震で振動を感じる
現在お住まいで、小さな地震でも大きな揺れを感じる場合は、建物の耐震性が低下している可能性が高いです。とくに、壁や接合部が劣化していたり、構造のバランスが悪くなっていたりすると、揺れが大きく感じられます。
このような問題がある場合、耐震診断を早期に受けることが重要です。ただし建物だけでなく、前述した地盤の状態が影響する場合も考えられます。

木造戸建ての耐震補強方法は?
・基礎の補強
・柱を金具で補強
・壁の補強
・屋根の軽量化
・塀の補強
・地盤の強化
ここからは、木造の戸建ての具体的な耐震補強方法について紹介します。
基礎の補強

築年数が古い木造戸建ては、基礎のコンクリートが劣化してクラック(ひび割れ)が生じていたり、コンクリート内部の鉄筋が入っていないケースがあります。クラックについては、樹脂を流し込むことで補修が可能です。鉄筋が入っていない無筋基礎の場合は、コンクリートを追加で打設(打ち増し)することで補強します。

1995年の淡路・阪神大震災は直下型地震であり、真下から突き上げるような縦揺れによって、柱が土台から飛び出してしまう「ほぞ抜け」が多く発生しました。この「ほぞ抜け」を防ぐためには、ホールダウン金物を使用して柱と土台をしっかりと固定する耐震補強が有効です。
また、白アリによる食害や湿気による腐食によって柱が劣化すると、建物倒壊の原因になることがあります。このような場合には、劣化した部分を取り除き、新しい柱に入れ替えたうえで金具を使用し、確実に固定します。
柱の劣化を根本から防ぐ対策としては、地面からの湿気を遮断するための防湿シートを敷くことや、白アリの駆除、防蟻処理を施した建材の使用などがあります。CRAFTでは状況に応じてベストな方法をご提案しています。
壁の補強
日本の木造戸建ての多くに採用されている「木造軸組工法(在来工法)」は、垂直な柱と水平な梁を組み合わせた工法で、横方向の揺れに弱いといわれています。そんな木造住宅の耐震性を高めるのが、水平方向に掛かる力に抵抗する「耐力壁」を追加するリフォームです。
柱と柱の間に強度の高い構造用合板を追加したり、斜めに「筋交い」を追加したりすることで、耐震補強ができます。また、「耐力壁」の追加は横揺れ対策にも有効です。
屋根の軽量化

昔から日本で使用されてきた陶器製の瓦は、1枚3kgほどと非常に重いです。一般的な戸建てで使用されている瓦の総重量は自家用車2~3台分ともいわれ、大きな地震の際に建物が屋根の重みに耐えられず倒壊する事例もあります。
屋根の耐震補強のポイントは、軽量化です。リフォームで使用する屋根材として代表的な「ガルバリウム鋼板」は、軽量で耐久性も高いと言われています。
塀の補強
地震の際、倒壊した塀によって通行人が下敷きになる事例もあります。とくに危険度が高いのは、セメントなどを用いずに組んだだけの石積みの塀です。
また、一見頑丈そうに見えるブロック塀も、モルタルや鉄筋が適切に使用されていないものは倒壊の危険性があります。 倒壊の可能性がほとんどなく安全性が高いのは、塀の代わりに木を植えた「生け垣」です。「生け垣では防犯面で不安」という場合には、軽量な素材のフェンスなどを活用する方法があります。
地盤の強化
いくら基礎がしっかりしていても、地盤が軟弱であれば地震時に住宅が大きく傾くリスクが大きくなります。地盤の強化には、建物の下を採掘して油圧ジャッキで支えながら杭をする方法や、特殊な薬剤を地面に注入して固める方法などがあります。
耐震補強にかかる費用は?補助金や減税制度の活用方法
耐震補強は重要ですが、費用面で不安に思う方も多いです。ここでは、耐震補強の費用目安や利用可能な補助金、税制優遇について詳しくご紹介します
一般的な耐震補強費用の目安
| 耐震補強の種類 | 費用の相場 |
|---|---|
| 基礎の補強 | 50〜150万円程度 |
| 壁や筋交いの補強 | 30〜50万円程度 |
| 屋根・梁・柱の補強 | 50〜150万円程度 |
| 上記を含む全体の補強 | 100万円~500万円程度 |
CRAFTはフルリフォームと併せて耐震補強を行っているため、耐震補強費用は上記の限りではありません。詳しくは直接お問合せください。
耐震補強の補助金
耐震補強を行う際、多くの自治体では、耐震診断や補強工事に対して補助金を支給する制度があります。補助金の額や対象条件は地域によって異なりますが、一般的には数十万円までの支援が受けられることが多いです。
自治体の補助金制度を利用するためには、条件や申請期限があるため、事前にお住まいの自治体に確認しておきましょう。
所得税の特例措置
耐震補強工事を行う際、所得税の特例措置を利用することで、税金を軽減することができます。
<特別控除の内容>
耐震改修工事の費用のうち、一定額(最大25万円)が所得税から控除されることがあります。
控除額は、工事費用や住宅の種類によって異なります。
一般的には、工事費用の10%(上限が25万円)程度が控除対象となることが多いです。
この特例措置は、耐震基準を満たしていることが条件となります。また工事終了時には、リフォーム会社からの証明書が必要です。

戸建ての耐震リフォームの流れ
1.現地調査、ヒアリング
2.耐震診断の実施
3.補強プランの作成・見積り提出
4.耐震補強工事の実施
5.完了検査・引き渡し
CRAFTの耐震リフォームの流れは、上記の通りです。各ステップについて詳しく解説します。
1.目視チェック
フルリフォームでは一旦建物を構造のみに解体します。その際に、基礎に問題はないか、外壁や屋根、屋内の床や梁等に劣化はないか、シロアリによる被害はないかといった点を目視で確認します。
2.耐震診断の実施
現地調査とヒアリングの結果を踏まえて、綿密な調査が必要な場合は、CRAFTのパートナーである構造設計事務所に依頼して耐震診断を行い、地震に対する耐力を測ります。
構造設計事務所は、まず設計図書をもとに建物を確認し、次に現地調査でコンリートのクラックや鉄筋のさびといった劣化状態、コンクリートの圧縮強度を測ります。
3.補強プランの作成・見積り提出
耐震診断の結果を踏まえて、耐震補強工事のプラン、費用のお見積りを作成します。
現在の戸建て住宅の状況によって、行うべき耐震補強工事の内容や施工範囲は異なります。大規模な補強工事になるほどかかる費用も増すため、見積りの詳細をよく確認しましょう。
4.耐震補強工事の実施
作成したプランに沿って、耐震補強工事を進めます。耐震補強を伴う大規模なリフォームは、必ず仮住まいが必要です。CRAFTでは仮住まい先やトランクルームのご紹介も行なっています。
5.完了検査・引き渡
耐震補強工事が完了したら、完了検査を行います。施工状態に不備がないかどうか確認を行い、問題がなければ工事完了・引き渡しです。安全で長く住める家にするためにも、信頼できる専門会社へ相談を行いましょう
信頼できる耐震補強会社選びのポイント

会社選びのポイント
・フルリフォームに対応している
・耐震補強の実績がある
耐震補強は建物の構造に関わるため、知識と実績のある会社に依頼することが重要です。CRAFTはフルリフォームに対応し、木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造の耐震補強実績も豊富にあります。
パートナーの構造計算事務所と連携しながら、現行の耐震基準まで性能を引き上げ、自社設計・施工により高品質な補強工事のご提供が可能です。
CRAFT青山ショールームでは見学・相談会を開催しています。耐震リフォームについてお気軽にご相談ください。
「中古」で戸建てを買ったら、耐震補強すべき?
耐震補強の必要性は、築年数(耐震基準)や建物の形状、壁量など、総合的な判断が必要です。リフォーム会社などに建物の状態をチェックしてもらい、必要があれば耐震診断の上、補強を検討しましょう。
ただし、中古の戸建ては「築年数や見た目からは、耐震性能がわかりづらい」というデメリットがあり、購入自体の判断を迷ってしまうケースがあります。そこでCRAFTの中古物件仲介サービスでは、物件の内見に建築のプロが同行し、建物調査を実施しています。
問題がなければ(※)「瑕疵保険」を無料でサービス。とくに、不具合が発生しやすい「構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁など)」と「雨漏りを防止する部分(屋根、外壁など)」は5年間保証対象となっています。
(※)建物調査によって不具合が見つかり、瑕疵保険の加入条件を満たせない場合でも、リノベーション工事と一緒に該当箇所を修繕することで、同様の保証を無料で受けることができるため、ご安心ください。
木造戸建ての耐震補強リフォーム事例

築50年の木造戸建てをフルリフォームした事例です。旧耐震基準で建てられていたため、木造軸組部分を補強し、耐震性を高めました。さらに解体時に内部の基礎を確認したところ、ひび割れなど劣化していた箇所が見つかったため、基礎の両面に炭素繊維シートを貼って補強しています。
戸建ての耐震補強リフォームでよくある質問
Q戸建ての耐震補強にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 戸建てのフルリフォーム期間は、計期間3ヶ月~ / 工事期間4~6ヶ月ほどかかります
耐震補強を含めた、戸建てのフルリフォーム期間は、計期間3ヶ月~ / 工事期間4~6ヶ月ほどです。ただし建物の規模や建物の劣化状況、工事内容によるため、詳しくはお問合せください。また工事期間中は、振動やほこりの発生、複数の作業員の出入りなどがあるため、仮住まいをおすすめしています。CRAFTは仮住まいやトランクルームもご紹介していますので、お気軽にご相談ください。
Q戸建てを耐震補強すると資産価値は上がりますか?
A. 耐震補強により建物の安全性が向上し、資産価値は上がる可能性は高くなります。
耐震補強を実施することで、建物の耐震性が高くなります。これは買い手にとっては非常に魅力的で、将来の売却時には査定額が向上する可能性もあります。また、今後の修繕や改修にかかる費用が削減される点も大きなメリットです。
Q耐震補強と建て替えはどちらがよいでしょうか?
A. 建物の状況やご希望によってどちらがベストかは異なります。一度、ご相談ください。
耐震補強と建て替えの選択は、建物の状態やご希望内容、費用を考慮する必要があります。一般的には、耐震補強は建て替えよりもコストを抑えられる場合が多いですが、構造的に大きな問題がある場合や補強が難しい場合は、建て替えを検討する方が適切です。どちらか迷っている場合も、CRAFTへご相談ください。
Q DIYでできる耐震補強はありますか?
A. 一部の対策はDIYでも可能ですが、フルリフォーム専門の会社に依頼するほうが安全で確実です。
簡単な耐震補強(家具の固定や壁の補強など)はDIYで行うことができますが、構造に関わる本格的な補強には専門的な知識や技術が求められます。とくに基礎や耐力壁、柱の強化などは、建物全体の安全性に影響を及ぼすため、専門会社に依頼することが最も安全で確実です。
〈DIYでできる耐震対策例〉
•家具を固定する(L字金具・突っ張り棒の使用)
•窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る
•壁や天井に補強材を設置(耐震パネルなど)
〈フルリフォーム専門会社に依頼すべき補強〉
•耐震壁の設置
•基礎の補強(ひび割れ補修・コンクリート補強)
•屋根の軽量化
•梁の補強
〈まとめ〉古い戸建てはリフォーム時に耐震補強も検討しよう
耐震性に不安がある古い戸建ては、まず耐震チェックを受け、必要に応じて補強を検討しましょう。耐震性を高めることで、資産価値も向上します。耐震壁の設置や基礎補強などは、耐震リフォームの実績豊富な会社に依頼することが大切です。
CRAFTは1982年創業のフルリフォーム専門会社として、数多くの耐震補強を行ってきました。リフォーム時には耐震チェックを行い、必要に応じて新築レベルに耐震性を向上させる補強方法をご提案。併せて、間取り変更やデザイン性向上も叶えます。安心して住み続けられる、美しく快適な住まいに一新しましょう。

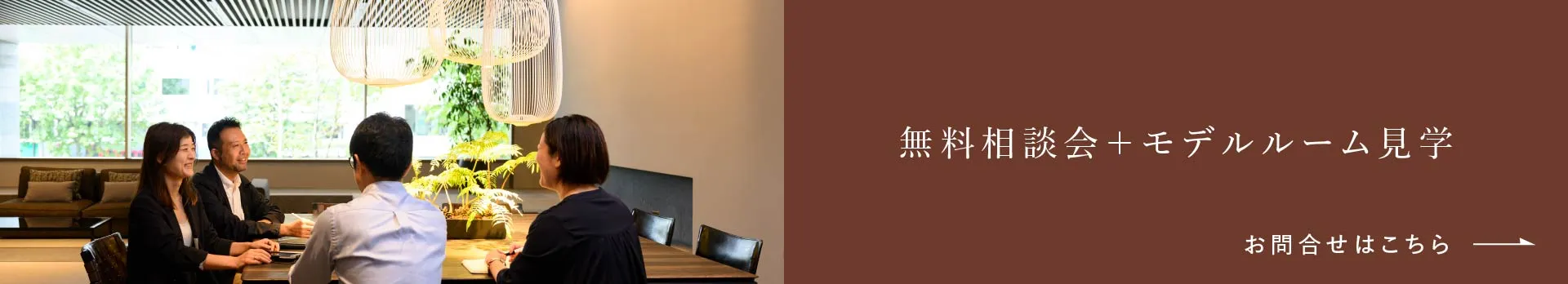

<著者>CRAFT 編集部
一級建築士・二級建築士・インテリアコーディネーター・一級建築施工管理技士・二級建築施工管理技士・宅地建物取引士が在籍。さまざまな知識を持つプロフェッショナル集団が、リノベーションや物件購入についてわかりやすく解説します。








